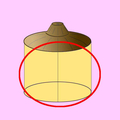平安時代の衣装。
平安時代の衣装について調べてみました。
女性の衣装。
女性の衣装といえば十二単衣。
しかし作中の説明によると、宮中に参内する際は十二単衣。自宅にいるときは普段着で過ごすとのこと。
自宅にいても、小萩のように主人に仕えている女房のみ十二単衣になるようです。
それでは十二単衣と普段着はどう違うのでしょう。
十二単衣の着付けを解説しながら普段着との違いを具体的にみていきましょう。
- 小袖。
まずは、この格好からスタート。神社の巫女さんのような衣装ですね。
就寝時はこれに近い格好ではないかとおもいます。

- 単。
小袖の上に単を重ね着します。夏場はこの格好で過ごしたりもします。

- 袿。
単の上にさらに袿を重ね着します。
これが、普段着。冬場は袿を何枚も重ね着して過ごします。
作品の挿絵などでお馴染みですね。

袿では動きにくいので、動きやすくするため小袿を着たりもします。袿よりもゆきたけが短いのが特徴です。

- 打衣。
袿の上にさらに打衣を重ね着します。

- 唐衣。
いよいよ十二単衣と呼ばれる格好になります。
袿を重ね着し、その上にさらに唐衣を重ね着します。
これが、礼装。作中では瑠璃姫が後宮にもぐりこんだ時の衣装です。

これに前に小腰。

これに後ろに裳。

さらに後ろ両側に引腰。

手には檜扇、懐に帖紙を入れて完成です。
十二単衣といっても12枚着るのではなく袿を重ね着してせいぜい7、8枚といった所でしょうか。
しかし、これでは小萩は満足に動き回れないような気がしますね。
立ったまま眠れるような気さえしてきます。
にもかかわらず、瑠璃姫はこの格好で馬に乗り、松明を掲げてます。おそるべし瑠璃姫。
女性の外出着。
一生のうち数度しか外出しない「現代」の女性には、外出着がないように思われがちですが、
一応あります。
作中では、吉野から都に瑠璃姫と小萩が帰ってくる時に着ていました。
男性の衣装。
男性の衣装にも礼装と普段着があります。
男性の礼装。
男性の礼装は束帯といい、女性と違い文官と武官で違います。
礼装は宮中にあがる際や、特別な場合に着る衣装です。
男性の普段着。
普段は、直衣や狩衣で過ごします。