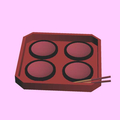用語解説
あ
- 葵
- 色の名前。表は薄青、裏は薄紫の襲。こんな色■。
- 網代車
- 略式の牛車。大臣などが使用した。

- 阿闍梨
- 師範たるべき高僧の称。
- 按察使
- 官職。諸国の民情を巡察した官。
- 甘葛
- アマチャヅルに当たるツル草の一種。ツルを切った液を集めて甘味料とした。
- 雨夜の品定め
- 源氏物語で五月雨の降る頃、光源氏を含む男性達が女性の品評会を行ったこと。
い
- 衣架
- 着物をかけておく道具。
- 石伏
- スズキ目の川魚。別名、ウキゴリ。
- 伊勢物語
- 平安時代の物語。作者不詳。
- 市女笠
- 衣装。菅または竹皮で編んだ笠。元々は市で商売する女性が使っていたためこの名がある。

- 乾
- 北西の方角。
う
- 有験
- 祈祷の効果のあること。
- 右近少将
- 官職。近衛府(皇居や行幸時の警護を行う役所)の次官。
- 丑寅
- 北東の方角。
- 薄縁
- 裏をつけ、縁をつけた筵で、家の中や縁側に敷くもの。
- 歌合
- 歌を詠みあって優劣をつける貴族の遊び。
- 右大将
- 官職。近衛府(皇居や行幸時の警護を行う役所)の長官。
- 右大臣
- 官職。太政大臣・左大臣の次の官職。
- 右大弁
- 官職。太政官直属の官。兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省を掌握した。その長官。
- 袿
- 衣装。女性の普段着。単よりもやや小さい服。単の上に着る。

- 打衣
- 衣装。単と同形で裏のついた和服。袿の上に着る。

え
- 葡萄染め
- 色の名前。浅い紫色。ぶどう色。こんな色■。
- 衛門督
- 官職。衛門府の長官。
- 衛門佐
- 官職。衛門府の次官。
- 衛門大尉
- 官職。衛門府の三等官。
- 衛門府
- 役所。門や京の警備などを行う役所。後に検非違使がとってかわる。
- 円座
- 円形の敷物。別名、わろうざ・わらうだ。

お
- 折敷
- 四方に折りまわした縁をつけた、へぎ製の盆。食べ物や飲み物を盛る。
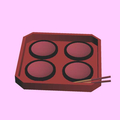
- 白粉
- 顔に塗る白い化粧のこと。
- 落窪物語
- 平安時代の物語。作者不詳。
- 小野小町
- 平安時代の歌人。「花の色は移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」の作者。