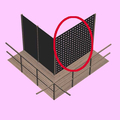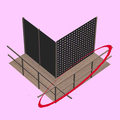用語解説
か
- 蜻蛉日記
- 平安時代の日記。右大将道綱の母の作品。
- 加持
- 祈祷を参照。
- 方違え
- 外出する前夜、吉方の方角の家に一泊して方角を変えて行くこと。
- 看督長
- 官職。検非違使の属官。罪人の追捕などを行った。
- 髪箱
- 女性が寝る際、長い髪をとぐろのようにまいて入れておいた箱。
- 賀茂祭
- 5月15日(陰暦四月の中の酉の日)に行われる祭。
- 唐衣
- 衣装。女性の礼装の上着。袿の上に着、後ろに裳や引腰をつけるのが特徴。

- 狩衣
- 衣装。男性の普段着。肩に切れ込みが入り、前に布がたれ、袖に紐があるのが特徴。

- 家令
- 親王・内親王・三位以上の家の家務・会計をつかさどった職員。後に家司にとって変わる。
- 関白
- 天皇を補佐した最高位の大臣。
き
- 北の方
- 貴族の妻のこと。
- 几帳
- 台に柱をかけて、とばりをかけたもの。部屋の仕切りに使った。

- 牛車
- 牛にひかせた貴族の乗り物。
- 紀伝道
- 歴史書や文学を学び、作文を習う学問。
- 祈祷
- 神仏に祈ること。
- 伽羅
- インド・中国の南方に産する香木。高級な数珠の原材料に使われる。
- 脇息
- ひじかけ。座った時に、ひじをもたれて体を休ませる道具。

- 禁色
- 位によっては仕えない色のこと。
- 今上帝
- その時代の天皇のこと。
- 公達
- 男性貴族のこと。
く
- 櫛箱
- 櫛などの化粧道具を入れておく箱。
- 朽葉色
- 色の名前。オレンジに近い。こんな色■。
- 蔵人頭
- 官職。蔵人所(天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の雑事を掌る役所)の長官。別名、頭の中将。
- 蔵人
- 官職。蔵人所(天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の雑事を掌る役所)の職員。
- 車宿
- 車を入れておくための建物。今で言うガレージ。
け
- 経机
- 経を読む際にお経をのせる机。きょうつくえ。

- 家司
- 官職。親王・摂関・大臣・三位以上の家の家務をつかさどった職員。
- 外記
- 官職。少納言の下で公事をおこなった。
- 潔斎
- 酒、肉を断ち、行いを慎み、心身を清めること。
- 闕腋袍
- 衣装。男性の衣装。裾がなく両脇を開けて動きやすくしているのが特徴。

- 検非違使
- 役所。治安・検察・裁判を行う。兵部省より後に設置された。
- 権門
- 官位が高く、権勢のある家柄や人。
- 源氏物語
- 平安時代の物語。紫式部の作品。
こ
- 後宮
- 后妃などの住む、宮中の奥御殿。
- 格子
- 細い木や竹を縦横に組んで取り付けた戸や窓。上半分だけを外へななめに開ける場合もある。
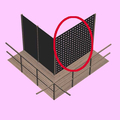
- 小袿
- 衣装。女性の衣装。袿よりもゆきたけが短い。

- 勾欄
- 端の反り返った欄干。
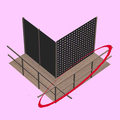
- 固関使
- 官職。政変などの非常事態に際して、関を封鎖して通行を禁じる人。
- 国司
- 官職。朝廷から諸国に任命された地方長官。諸国に赴任しない者もいた。
- 小腰
- 衣装。女性の衣装。礼装の時、前にたらした装飾。

- 小柴垣
- 小さい柴で作った垣。
- 御諚
- 貴人の命令。おことば。
- 五節の舞姫
- 新嘗祭・大嘗祭で舞を踊る姫のこと。
- 小袖
- 衣装。袖が小さい普段着。袖口がせまいのが特徴。男性も着用した。

- 木霊
- 木の精。
- 近衛の少将
- 官職。右近少将のこと。
- 近衛舎人
- 官職。近衛府(皇居や行幸時の警護を行う役所)の兵士。
- 権侍医
- 官職。侍医(天皇の診察医)の下で働く医者。
- 権少将
- 官職。仮の少将のこと。権とは仮を意味し、定員外に置いた地位を表す。
- 権中将
- 官職。仮の中将のこと。