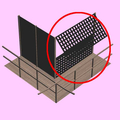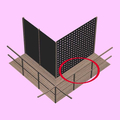用語解説
さ
- 左衛門佐
- 官職。左衛門府の次官。衛門府には左衛門府と右衛門府がある。
- 左京少進
- 官職。左京(京の東側)の司法、行政、警察を行う三等官。
- 指貫
- 衣装。衣冠・直衣、または狩衣の時にはいた袴。すそをふくらませてくくる。

- 左大臣
- 官職。太政官の長官。太政大臣の下。右大臣の上。
- 左中弁
- 官職。太政官直属の官。中務省・式部省・治部省・民部省を掌握した。その次官。
- 左馬頭
- 官職。左馬寮(馬の飼育や調教などを行う役所)の長官。
- 侍烏帽子
- 衣装。武官が主に用いた烏帽子。

- 更科の月
- 姥捨て山の月。転じて年を取ることをなげく意味に使われる。更科日記が由来とも。
- 参議
- 官職。大中納言に次ぐ重職。宰相。奈良時代に設けられた令外の官。
- 参内
- 宮中に参上すること。
- 三位中将
- 近衛中将で三位の位になった人。中将は普通四位。
し
- 紫苑襲
- 表は薄紫色。こんな色■。裏は青色の襲。
- 式部卿
- 官職。式部省(役人の人事・教育・儀式を行う役所)の長官。
- 式部丞
- 官職。式部省(役人の人事・教育・儀式を行う役所)の三等官。
- 脂燭
- 宮中で夜間に用いられた照明器具。
- 蔀戸
- 格子によく似た戸で、上下に開閉した。重いので、上下に分かれているものを半蔀という。
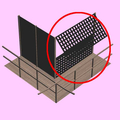
- 除目
- 大臣以外の諸官を任命した儀式。
- 下部
- 召使・下男のこと。
- 従五位
- 官位。従四位の下。数字が少ないほど位が高い。
- 入内
- 皇后が一定の儀式を整え、実質的に内裏に入ったこと。
- 荘園
- 貴族が持っている土地。
- 少将
- 官職。近衛府の次官。
- 精進潔斎
- 飲食を慎み身体をきよめ、けがれを避けること。
- 少納言
- 官職。太政官の三等官。
- 沈
- ジンチョウゲ科の常緑香水。別名、沈香。
- 寝殿
- 貴族の住まい。
す
- 水干
- 衣装。狩衣の一種。前に布がたれていないのが特徴。元は民間の普段着。後に公家の私服や少年の晴れ着になった。

- 蘇方
- 色の名前。黒みを帯びた紅色。こんな色■。
- 典侍
- 官職。内侍典侍のこと。
- 修法
- 密教で行う加持祈祷の作法。
- 受領
- 官職。朝廷から諸国に赴任した地方長官。国司が諸国に赴任しない場合、受領が事実上の地方長官。
- 簀子縁
- 廊下のこと。
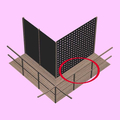
せ
- 摂関家
- 天皇が幼少・病気の際に、代って政治を行う家柄のこと。
- 背の君
- 夫の尊敬語。
- 践祚
- 皇嗣が天皇の後をつぐこと。
そ
- 雑司
- 宮中で雑用を務めた職。またはその職の者。
- 雑色
- 院・御所に属して雑役を務めた職。またはその職の者。
- 雑舎
- 召使のいる建物。
- 筝の琴
- 楽器。13弦の琴のこと。

- 束帯
- 衣装。男性の礼装。